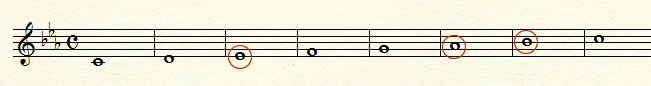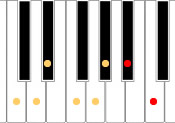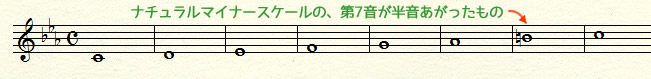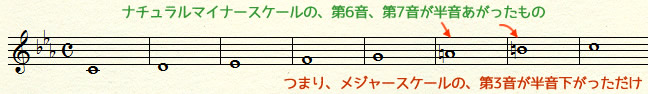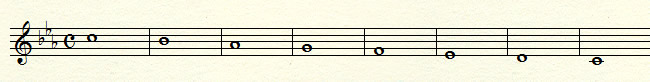キーボードを担当していて感じたことや、戸惑ったことなども素直に書いた、初心者のためのちょっとしたアドバイスのサイト。
暇つぶしの読み物としてもどうぞ。通勤通学のなどの空いた時間にでも。
マイナースケール
前にも書いた通り、マイナースケールには大きくわけて3種類ある。
自然的短音階(ナチュラル・マイナー・スケール)
和声的短音階(ハーモニック・マイナー・スケール)
旋律的短音階(メロディック・マイナー・スケール)
です。
マイナースケールは、調号が必要ないのはAmなので、よくAmが例に挙がることが多いけど、
メジャースケールとの違いを分かりやすくするために、あえてCmで説明します!
調号を見てわかるとおり、
ミとラとシがフラット。
つまり、メジャースケールから、第3、6、7音がフラットになったものがナチュラルマイナースケール。
特に大事なのが、第3音。
この音がフラットすると、他が何であれマイナー系のスケールになる。
そして、ナチュラルマイナースケールは、第7音もフラットになる。
ということはつまり、
↑っていう感じで、赤いとこ見てください。
第7音と第8音(ルート音)との間が1音あくことになる。
第7音は結構大事な音で、最も主音(ド)に進みたがる音とされている。
特にルートの半音下のシは導音と言って、ルートに落ち着くためにものすごい役割を果たすのである!
・・・が、上記のとおり、ナチュラルマイナースケールは、シがフラットになっていて、導音が含まれてない。
これはなんだかな~
って誰かが思ったのかは知らないけど、そんないきさつで生まれたのが、この第7音に導音を用いたハーモニック・マイナー・スケール!
弾いてみるとわかるけど、なんかこう日本的な響きというか、
特にラとシの間が1音半もあいてるのでちょっと変な感じがすると思う。
日本語名では「和声的短音階」っていうのも、わかるわかる~って感じ。
が、やっぱり気になる~ってこれも誰かが思ったのかは知らないけど、
それならこの「ラ」と「シ」の間をちょっと狭めましょう・・・・っていうことで生まれたのが、メロディック・マイナー・スケール。
「ラ」が半音上がって違和感なくなりました!!
で、気が付いたら第6音と7音はメジャースケールと同じになってるんですよね。
第3音がフラットしただけ。
覚えやすいですね!
・・・が、このスケール、なんと上りと下りで音が違うんです。
導音が必要なのは、音階を上るときだけ・・・つまり、「シ」→「ド」っていう進行が欲しかっただけなので、
下りの場合はべつに「シ」がナチュラルにならなくてもよいわけです。
というわけで、メロディックマイナースケールの下りは、
↑こうなる。
気づきましたでしょうか。
下りはナチュラルマイナースケールとおんなじ!
・・・だからなんだ!と言われても困っちゃうんですが、理由を考えれば、あ~なるほど~って感じですよね!
で、これがどう役にたつのか
といいますと、
とりあえずハーモニックとメロディックはおいといて、ナチュラルマイナースケールを頭に叩き込むべく、弾いてください。
スケールが頭に入ると、フレーズがすごく弾きやすくなります。
耳コピをしてると、「聴いた曲をすぐに弾く」っていうことをしないといけなくなるんだけど、
この時音をさぐりさぐりやってると時間がかかる。
でも、スケールが頭に入ってると、これがささーーーっと、すすーーーっとできるようになるんですよフシギですね!
ちょっと変わったコードやフレーズがでてきたりしても、
メジャースケールとマイナースケールを基本として一部がちょっと違う っていう考え方になる。
土台があると、頭の中で整理がしやすくなるんです。
速く弾くことが目的じゃありません。
音名とともに、頭に音を入れること!
これが重要なのです!!
・・・・って言ってますが、この先ペンタトニックやらブルーススケールやら出てくるんですが、これはこれで「弾けるようになるため」練習が必要だったりします。
まあでもそれは、メジャースケールとマイナースケールを基礎としたうえでやることをお勧めします!
というわけで次は・・・何のスケールにしようか考えてます・・・